Jリーグ創設時から存在する「オリジナル10」は、日本サッカーのプロ化の出発点として多くのファンに語り継がれてきました。今やJリーグは全国にクラブが広がり、多様性を持つリーグとなりましたが、その原点ともいえるクラブたちには、歴史・誇り・変遷があります。
- そもそも「オリジナル10」とは何か?
- どんなクラブが選ばれたのか?
- 現在はどんな立場にあるのか?
本記事では、オリジナル10のクラブ紹介から現在の立ち位置、そしてこれからの展望までを網羅的かつわかりやすく解説していきます。
Jリーグのオリジナル10とは何か?
「Jリーグオリジナル10」とは、1993年5月に開幕したJリーグ(日本プロサッカーリーグ)の初年度に参加した10クラブの総称です。この呼称はサッカーファンの間で広く使われ、日本サッカー界のプロ化の象徴とも言える存在として知られています。発足当初の熱狂、地域と共に歩むクラブの姿勢、そして今日までの変遷など、「オリジナル10」という言葉には数多くの歴史と想いが詰まっています。
オリジナル10の意味と由来
「オリジナル10(Original 10)」という言葉は、英語で「最初の10の存在」を意味します。これはJリーグがまだ10クラブのみで構成されていた1993年の初年度にリーグへ参入したクラブに与えられた称号です。この言葉は公式に定義されたものではありませんが、ファンやメディアの間で定着し、特別な響きを持つキーワードとなっています。
発足当時の背景と目的

Jリーグは、当時「サッカー不毛の地」とまで言われた日本でサッカー文化を根付かせ、世界に通用する代表チームを作るという明確な目的のもと誕生しました。背景には以下のような要因があります:
- 1992年のバルセロナ五輪での活躍を受けた人気上昇
- 日本代表の国際大会での不振を打破するための体制強化
- 国民にサッカーを「魅せる」プロスポーツとして提示したいというビジョン
吹き出し:
「プロ野球しか知らなかった自分にとって、1993年のJリーグ開幕は衝撃だった。あのスタジアムの一体感、カラフルなユニフォーム、全部が新鮮だった!」
Jリーグ創設時の日本サッカーの状況
プロ化以前の日本のサッカーは、いわゆる「JSL(日本サッカーリーグ)」によって構成されていました。企業チームが中心で、観客数は1試合あたり数千人にも満たない状態でした。ところが、Jリーグがスタートすると、初年度から観客動員は爆発的に増加し、テレビ放映権やグッズ収益など、「サッカーでビジネスが成り立つ」という事例を作ったのです。
オリジナル10のクラブ選定基準
Jリーグ参入にあたり、クラブにはいくつかの厳しい条件が課されていました。具体的には:
- 地域密着型の運営体制を整備していること
- プロ契約選手を一定数以上抱えていること
- 観客席を持つ専用スタジアムまたは拠点スタジアムを確保していること
- スポンサー、ユニフォーム、エンブレムなどのブランド整備
この条件を満たし、JSL(前身の企業リーグ)から転換したクラブ、そして新設されたクラブも含め、10チームが正式にJリーグの初期メンバーとなりました。
オリジナル10が持つ象徴的な意味
オリジナル10は、単なる古株というだけでなく、日本サッカーの夜明けを切り開いた存在です。彼らの奮闘があったからこそ、Jリーグは世界に誇れるリーグへと成長し、W杯常連国という地位を得られたとも言えます。
オリジナル10のクラブ一覧と特徴
ここではオリジナル10に名を連ねたクラブの一覧と、簡単な特徴を紹介します。
| クラブ名(当時) | 現在の名称 | 本拠地 | クラブの特徴 |
|---|---|---|---|
| 読売クラブ | 東京ヴェルディ | 東京(旧川崎) | Jリーグ開幕戦勝利、スター軍団 |
| 日産FC | 横浜F・マリノス | 神奈川県横浜市 | 技術的で魅せるサッカー |
| 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 茨城県鹿嶋市 | 最多タイトル獲得の名門 |
| 浦和レッズ | 浦和レッズ | 埼玉県さいたま市 | 日本一のサポーター文化 |
| 清水市民クラブ | 清水エスパルス | 静岡県清水市 | 唯一の市民クラブ型 |
| 名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパス | 愛知県名古屋市 | 中部地方の雄 |
| ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | 大阪府吹田市 | 攻撃的なパスサッカー |
| サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | 広島県広島市 | 育成に定評あるクラブ |
| 横浜フリューゲルス | 消滅(横浜FMと合併) | 神奈川県横浜市 | 合併で消滅した名門 |
| ジェフ市原 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉県市原市 | 地元密着と一体感 |
所属クラブの地域と分布
日本列島の東西にバランスよく分布しており、地域の人口や企業基盤を考慮した形となっていました。関東・東海・関西・中国地方に集中しており、北海道や東北、四国、九州は初年度には参入していません。
各クラブのスタイルやファン層の違い
クラブごとに戦術・カラーが異なります。たとえばガンバ大阪はパスサッカー、鹿島アントラーズは堅守速攻、浦和レッズは熱狂的なサポーターによる圧力が特徴です。ファン層も地域によって異なり、家族連れ重視や若者層中心など、スタジアムごとに雰囲気が変わります。
共通点と個性のバランス
オリジナル10は、地域密着という共通理念を持ちながらも、戦術や経営方針、ファン文化には個性があり、Jリーグが多様性を持つことに成功した要因にもなっています。これこそが、30年を超えてもなお「オリジナル10」の名が語られる理由なのです。
オリジナル10の成績と実績の比較
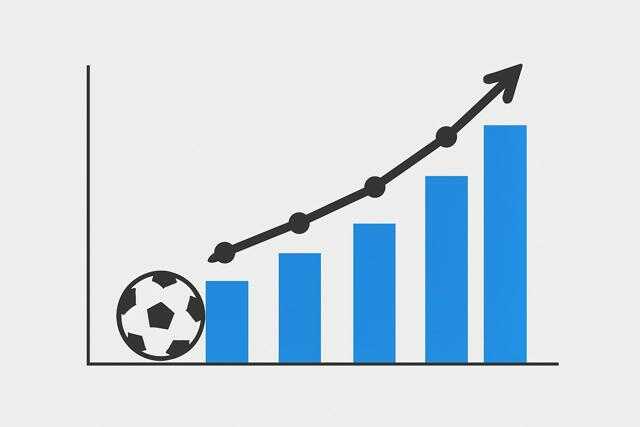
Jリーグオリジナル10と呼ばれる10クラブは、それぞれがプロサッカー元年からリーグに参加し、長年にわたりJリーグをけん引してきました。彼らの功績と実績は、ただ単に「古参クラブ」で終わらせるには惜しいほどの深みがあります。
Jリーグ優勝回数・タイトル数
最も多くのタイトルを獲得しているのは鹿島アントラーズです。J1リーグ最多優勝記録を保持し、天皇杯、ルヴァン杯、スーパーカップなど国内主要大会を総なめにしてきました。
以下は、オリジナル10のクラブが獲得した主なタイトルの一覧です:
| クラブ名 | J1優勝 | 天皇杯 | ルヴァン杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 8回 | 5回 | 6回 | 1回 |
| 横浜F・マリノス | 5回 | 7回 | 2回 | 0回 |
| 浦和レッズ | 2回 | 4回 | 2回 | 2回 |
| ガンバ大阪 | 1回 | 2回 | 2回 | 1回 |
| 名古屋グランパス | 1回 | 2回 | 2回 | 0回 |
こうした結果を見ると、オリジナル10の中でも実績に大きな差があることがわかります。鹿島は安定して強く、タイトルを取り続けている一方で、未だ主要タイトル未獲得のクラブも存在します。
アジア大会での成果
ACL(AFCチャンピオンズリーグ)において、オリジナル10からは浦和レッズと鹿島アントラーズ、ガンバ大阪がアジア王者に輝いています。これにより、日本サッカーの国際的評価も大きく向上しました。
- 浦和レッズ:ACL優勝2回(2007, 2017)
- 鹿島アントラーズ:ACL優勝1回(2018)
- ガンバ大阪:ACL優勝1回(2008)
これらのクラブがアジアの頂点に立ったことで、Jリーグのブランド力と競技力が一段階上がったと言えるでしょう。
近年のリーグ順位推移
オリジナル10のうち、安定してJ1に在籍し続けているクラブもあれば、J2やJ3へ降格し長く苦しむクラブもあります。以下に一部クラブの直近5年間のJ1順位推移を示します。
| クラブ名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 3位 | 5位 | 4位 | 5位 | 4位 |
| 横浜F・マリノス | 1位 | 9位 | 2位 | 1位 | 2位 |
| 浦和レッズ | 14位 | 10位 | 6位 | 3位 | 7位 |
吹き出し:
「伝統あるクラブがすべて強いわけではない。浮き沈みもまた、クラブが歴史を刻む醍醐味だと思う」
オリジナル10の現在の立ち位置

オリジナル10と呼ばれるクラブたちは、Jリーグの発足とともにスタートラインに立ちましたが、30年の時を経てその立ち位置は大きく変化しています。今もなおJ1で安定した戦績を誇るクラブがある一方で、J2やJ3に所属し再起を目指すクラブ、さらには消滅したクラブも存在します。このセクションでは、それぞれのクラブが現在どのカテゴリーに所属し、どのような状況にあるのかを整理しつつ、昇格・降格の歴史、そしてクラブ経営や観客動員のトレンドまでを解説します。
J1・J2・J3での所属状況
2020年代に入り、オリジナル10のクラブは以下のように分かれています:
- J1:鹿島、横浜FM、浦和、広島、名古屋、G大阪
- J2:東京ヴェルディ、清水エスパルス、ジェフ千葉
- 消滅・統合:横浜フリューゲルス(1999年に横浜FMと統合)
J2に降格したクラブの多くはJ1復帰を目指し、育成や補強に力を注いでいます。
昇格・降格を経験したクラブ
実はオリジナル10の中で、J2降格を経験していないのは鹿島アントラーズのみです。他のクラブは大小問わず、昇格・降格を繰り返しています。
- 浦和:2000年に降格、翌年昇格
- G大阪:2012年に降格、2013年で昇格&翌年3冠
- 清水:複数回降格を経験
- 千葉:2009年以降J2定着
クラブ経営と観客動員の変化
経営面では地域密着型の運営が根付いており、クラブごとにイベント・PR活動が活発化しています。特に浦和レッズや清水エスパルスは地域連携を軸とした集客モデルを築き、毎試合1万人超の動員を誇ります。
一方で、人口減少・少子高齢化の影響を受け、地方クラブでは観客動員の減少傾向も見られ、新たな集客戦略が課題となっています。
オリジナル10がJリーグに与えた影響
オリジナル10のクラブは、Jリーグ黎明期から現代まで、日本のサッカー文化に多大な影響を与え続けてきました。彼らが築いた基盤があったからこそ、地方クラブの参入、スタジアムの発展、育成システムの整備など、リーグ全体が成長できたのです。
リーグ発展への貢献
1993年のJリーグ開幕時、サッカーはまだメジャーなスポーツではありませんでした。しかし、オリジナル10による熱戦、スター選手の登場、地域イベントの開催が、爆発的な人気を呼びました。
- 平均観客動員数:19,000人以上(1993年)
- テレビ視聴率:読売ヴェルディ vs 鹿島アントラーズ 21%
- 関連グッズ販売数:前年比300%以上
このような数値が物語るのは、オリジナル10の存在がリーグ成功の原動力だったということです。
スタジアム文化と地域密着
各クラブは専用または準専用スタジアムを活用し、「地域の誇り」として愛されてきました。浦和の埼玉スタジアム、清水のIAIスタジアム日本平、鹿島のカシマスタジアムは、いずれもホームスタジアムとしての機能を超えた“地域の象徴”となっています。
| クラブ | スタジアム | 観客数(平均) | 地元イベント |
|---|---|---|---|
| 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | 28,000人 | レッズフェスタ・防災訓練連携 |
| 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | 12,000人 | 商店街連動フェス・農産物PR |
| 鹿島アントラーズ | カシマスタジアム | 14,000人 | 高校・中学との連携プログラム |
若手育成とユースシステムへの影響
オリジナル10の多くは、Jリーグ初期からユース・ジュニアユース部門を設立し、育成環境の整備に取り組んできました。
たとえば、ガンバ大阪ユースからは堂安律、宇佐美貴史などが輩出され、世界で活躍しています。横浜F・マリノス、鹿島アントラーズも日本代表選手を多く輩出しています。
吹き出し:
「ユースからトップへ上がる選手を見ると、クラブの未来がつながっている感じがして嬉しくなる。10代の成長物語はファンの誇りです。」
今後のオリジナル10の展望と課題
オリジナル10のクラブは、30年の時を経て新たな局面を迎えています。本項では、伝統あるクラブが今後直面するであろう課題や、将来に向けた展望について考察します。時代とともに変わる観客層、収益構造、競争環境の中で、オリジナル10がどう進化し続けるかに注目が集まります。
経営の安定性と持続可能性
スポーツビジネスは予測不可能な要素が多く、経営の継続性は常に課題です。オリジナル10の多くは地域密着とスポンサー支援に支えられていますが、単年度赤字や観客動員数減少に悩むクラブも少なくありません。
- 地域連携型の収益モデル(例:地元企業との共同商品開発)
- グッズ販売・動画配信サービスによる収入多角化
- SDGs視点を取り入れた持続型クラブ運営
特に地方クラブは、社会課題とスポーツを結びつけることで、スポンサーや自治体との信頼関係を深めています。
新世代サポーターの獲得
現在の10代・20代にとって「Jリーグ=身近な存在」と感じさせるためには、デジタル接点の最適化が必要です。
その施策例として:
- TikTok・YouTubeによる選手の日常コンテンツ配信
- 推し活文化に対応した応援グッズ・SNSハッシュタグ連動
- 大学・専門学校とのコラボで就職活動連携
スタジアム観戦が「ライブエンタメ体験」として浸透すれば、リピート率向上も期待されます。
他クラブとの競争激化への対応
Jリーグ全体のレベルアップとともに、新規参入クラブの急成長も著しいです。特に、湘南ベルマーレ、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸などが若年層支持を急速に獲得しており、オリジナル10との競争が激化しています。
オリジナル10はその「伝統」を活かしつつ、「革新」を取り入れることが求められています。
吹き出し:
「新興クラブの勢いに焦る必要はない。けれど、変わる努力を止めてしまえば、歴史が足かせになることもある。」
今後のオリジナル10の展望と課題まとめ
Jリーグオリジナル10のクラブは、それぞれが独自の歴史を持ち、Jリーグ全体の成長を牽引してきました。時代とともに求められる役割は変わりつつありますが、地域とのつながりや若手育成への注力はますます重要となっています。
今後は単に伝統を誇るだけでなく、競争力を維持し続けるための新しい戦略が求められるでしょう。観客動員の工夫、デジタル対応、サポーター層の拡大など、各クラブがいかに柔軟に時代に適応するかが鍵となります。
この記事を通して、オリジナル10がこれからも日本サッカー界で輝き続けるために必要な視点とアプローチを共有できたなら幸いです。



