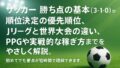- まずは洗浄→保護(湿潤タイプの絆創膏)で痛みと感染リスクを抑える
- 摩擦点にテーピングやパッドで「当たり」を分散する
- 蒸れ対策として速乾ソックス・中敷きの乾燥・靴内の換気を徹底する
足の皮がむける主な原因(摩擦・蒸れ・サイズ不適合・人工芝の熱)
サッカーの「皮むけ」は、繰り返すせん断力(摩擦)と長時間の湿潤(蒸れ)、そしてスパイクの当たり(圧力集中)や人工芝の高温が重なって起きます。
湿った皮膚は角層がふやけて強度が低下し、水ぶくれや表皮剥離に発展。特に母趾球・小趾球・踵・足背・アキレス周囲は負荷が集中しやすく、靴紐の締め具合や足型とラスト形状の不一致もトラブルを誘発します。
摩擦と圧力の集中
- 前足部の繰り返し停止・切り返しで局所のせん断が増大
- 硬いインソールや縫い目の段差が「ホットスポット」を形成
- 結び目やベロの折れで足背に線状の圧傷が生じやすい
汗・湿気による皮膚のふやけ
- 吸汗拡散できない素材や厚すぎるソックスで汗が滞留
- 試合後にスパイクを履き続ける習慣が乾燥遅延を招く
- 雨天の水分+体温上昇で角層強度が大幅ダウン
スパイクのサイズ・フィット不良
- トウボックスの高さ不足で爪上の皮膚が擦れる
- 踵カップの浮き→ヒールスリップ→水ぶくれ
- 足型(幅・甲高)とラストの不一致で当たり点が固定化
ソックス・インソールの素材と選び方
- 綿100%は乾き遅く摩擦増、混紡の吸湿速乾系が有利
- 裏パイルの段差・ロゴ刺繍が摩擦源になることも
- グリップソックスは滑りを減らすが当たりが強くなる部位に注意
人工芝の高温・やけどリスク
- 夏場はピッチ表面が高温化し、熱+摩擦で皮膚損傷リスク上昇
- 黒チップの付着で靴内温度が上がる→発汗増→ふやけ
| 部位 | 想定原因 | 即時対策 |
|---|---|---|
| 母趾球 | 切り返し時の前足部せん断 | 摩擦低減パッド+薄手速乾ソックス |
| 踵 | ヒールスリップ | 踵ロック結び+ヒールグリップ |
| 足背 | 紐の食い込み | アイレットスキップ+ベロ位置調整 |
| 小趾側縁 | 幅不足・縫い目段差 | 幅広ラスト検討+フェルトパッド |
原因は「一点」ではなく重なりやすい。摩擦・湿度・当たり・熱の4象限で考えると対策が明瞭になります。
すぐできる応急処置(湿潤療法と保護)

皮がむけた直後は「清潔・保護・湿潤」の3原則。無理に皮を除去せず、清潔な水で洗い流し、湿潤環境を保つドレッシングで覆います。必要に応じて圧力分散のパッドを併用し、練習復帰の可否は痛みと滲出量で判断します。
洗浄の手順と清潔保持
- 流水で砂やチップを除去(石鹸は刺激の少ないものを軽く)
- 清潔なガーゼで水分をそっと吸い取る(擦らない)
- アルコールなど強刺激の消毒は避け、必要最小限に留める
湿潤療法系絆創膏・セカンドスキンの使い方
- 創面より一回り大きいサイズで密着。角は丸く切ると剥がれにくい
- 滲出液が多い初期は吸収能の高いタイプを選択
- 創周囲にU字のフェルトパッドを置き、直接圧を逃がす
痛み・発赤・腫れなど感染兆候への対応
- 増悪する痛み、膿、発熱、赤い広がりは受診の目安
- 水ぶくれは基本は温存。破れた場合は清潔に洗い保護
- 糖尿病など創傷治癒に影響する背景がある場合は早めに相談
| 状況 | 推奨ドレッシング | 交換目安 |
|---|---|---|
| 軽度の擦過 | 薄手ハイドロコロイド | 1〜2日 |
| 中等度の剥離 | 厚手ハイドロコロイド+フェルト | 24時間〜滲出量で調整 |
| 破れた水疱 | 吸収パッド+保護テープ | 1日ごと |
やってはいけないこと:乾燥狙いの消毒連打、無理な皮の切除、通気の悪い厚重ね。
テーピングと保護パッドの実践
予防と再発防止の要は「滑りを減らし、圧を分散する」貼り方です。テーピングは端を丸め、皮膚にシワを作らないのが基本。摩擦予防の薄手テープ、ショック吸収のフェルト、摩耗に強いモレスキンを使い分け、練習中も剥がれたら迷わず貼り替えます。
摩擦予防の基本的な貼り方
- 皮膚を乾かし、必要ならプレテープスプレーを軽く
- ホットスポットに薄手の摩擦低減テープを「面」で貼る
- 縁は重ねて段差を作らない(端は外向きに丸める)
水ぶくれ保護と圧抜きのコツ
- 患部を囲むU字のフェルトでドーナツ状に圧を逃がす
- その上からハイドロコロイドを面で被覆、さらに摩耗対策の上貼り
- 靴内で擦れる方向(前後・左右)に合わせテープの流れを決める
練習・試合中の貼り替えタイミング
- 汗で浮いたら即交換。ハーフタイムは必ずチェック
- 痛みが減っても48〜72時間は保護継続
- 貼り替え時は必ず洗浄→乾燥→新規貼付の順
| 部位 | 推奨素材 | 目安の長さ・厚み |
|---|---|---|
| 母趾球 | 摩擦低減テープ+2〜3mmフェルト | 6〜8cm×2片 |
| 踵 | モレスキン+ハイドロコロイド | 踵幅+1cm余白 |
| 小趾側縁 | 薄手テープの帯+U字フェルト | 周径+重なり5mm |
ポイント:テープは「点」ではなく「面」で受ける。段差を作らない貼り重ねが長持ちのコツ。
スパイク・ソックス・インソールの見直し
用具の最適化は根本対策。ラスト形状・サイズ・甲の高さを見直し、結び方で踵の浮きを抑えます。ソックスは吸汗速乾と縫い目位置、インソールはアーチ支持とクッションのバランスで選び、当たりを面に分散させます。
フィット調整とサイズ選びのポイント
- つま先は5〜7mmの余裕、横は圧痛なしの密着
- 踵抜け対策に「ランナー結び(ヒールロック)」を活用
- ベロ位置のシワを整え、アイレットのスキップで甲の圧を調整
ソックス素材・重ね履きの可否
- 混紡(ポリエステル・ナイロン系)で吸湿拡散の良いもの
- 重ね履きは段差リスク。薄手+摩擦低減パッチ併用が現実的
- 裏パイルはクッション性と引き換えに摩擦増の可能性、要試行
インソール・パッドで当たりを分散
- 母趾球の痛みには前足部パッドで圧を後方へ逃がす
- 踵の擦れは深めのヒールカップとトップカバーの滑性で軽減
- 縫い目段差には薄フェルトでレベル出し(面当たり化)
| アイテム | 選び方の軸 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| スパイク | ラスト形状・甲高・素材伸び | 当たり点の減少・踵安定 |
| ソックス | 速乾性・縫い目配置・厚み | 湿潤時間短縮・摩擦低下 |
| インソール | アーチ支持・反発と緩衝 | 圧分散・疲労軽減 |
新調後は「30分×数回」の慣らし→全負荷へ。急な長時間使用は皮むけの近道です。
角質・乾燥対策と日常ケア
角質は「0か100」ではなく適量が理想。削りすぎはバリア低下と再肥厚を招きます。入浴後の保湿と軽いマッサージ、足部の機能トレーニングで皮膚と足の両面から強くし、季節や練習量でケア強度を調整します。
角質ケアはやり過ぎない
- 週1回の軽いやすりがけ。痛みが出る手前で中止
- ひび割れ部は削らず保湿と保護で落ち着かせる
- 血がにじむ削りは厳禁。保護パッドで機械的刺激を減らす
入浴後の保湿とマッサージ
- 入浴3分以内に保湿剤(尿素・グリセリン配合など)を薄く
- 足底筋膜に沿って母趾側へ軽擦。趾の付け根は優しく
- 就寝前は薄手ソックスで浸透サポート(蒸れすぎに注意)
足指・足裏の機能トレーニング
- ショートフット:土踏まずを軽く引き上げる10秒×10回
- タオルギャザー:足趾でタオルを手前に寄せる×3セット
- ヒールレイズ:母趾側に重心を感じながらゆっくり上下
| 習慣 | 頻度 | 目的 |
|---|---|---|
| 角質調整 | 週1 | 過度な肥厚の是正 |
| 保湿 | 毎日(入浴後) | 割れ・剥離予防 |
| 足トレ | 週3〜5 | 荷重分散・疲労軽減 |
皮膚ケア(バリア)+足機能(荷重制御)の二刀流が、再発しない足づくりの近道です。
予防ルーチンと受診目安
「練習前に仕込み、練習後にリセット。」このルーチン化が最強の予防です。用具の乾燥と衛生管理、気象条件への適応、負荷の波を作ること。悪化サインを逃さず、必要なときは早めに専門家へ相談しましょう。
練習前後のルーチン例
- 前:ホットスポットに薄テープ、必要に応じてU字フェルトを事前装着
- 前:ベロ位置と紐テンションを左右均等に、踵ロックでヒールスリップを封じる
- 後:靴内のチップ・汗を除去→中敷きを外して乾燥→入浴後に保湿
臭い・蒸れ対策と保管方法
- シューズは風通しの良い場所で陰干し。バッグ保管は厳禁
- 消臭・乾燥材をローテーション使用(凍結脱臭も有効)
- ソックスは裏返して洗浄し、繊維の目詰まりを防ぐ
深い剥離・強い痛み・発熱時は受診
- 広範囲の剥離、水疱の拡大、悪臭や膿があるとき
- 発熱・赤い広がり・ズキズキする痛みは細菌感染のサイン
- 既往(糖尿病・末梢循環障害など)がある場合は早期相談
| シーン | チェック項目 | 行動 |
|---|---|---|
| 試合前 | ホットスポット・紐テンション・ソックス乾燥 | 予防テープ・結び直し・替えソックス準備 |
| ハーフタイム | 痛みの出現・テープの浮き | 即貼り替え・ベロ位置リセット |
| 帰宅後 | 砂・湿気・チップ残存 | 洗浄・乾燥・保湿・用具の陰干し |
ルーチンはチーム全員で共有すると効果が跳ね上がります。予備のテープと替えソックスは常にバッグへ。
まとめ
「皮がむける」は摩擦と湿気の管理で大半が改善します。患部は清潔・湿潤で保護し、摩擦源(サイズ不適合・ソックス素材・結び方)を特定して修正。練習前後のルーチン(保湿・予防テーピング・乾燥)を習慣化すれば再発率は大幅に低下。
強い痛みや膿、発熱を伴う場合は早めに受診しましょう。